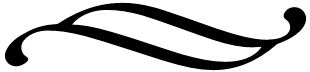アガ・モハマド・カーンは、ザンド最後の国王の死後の内戦で勝利を収めた後、イランの再統一と中央集権化に注力した。
[54]ナデル・シャーの後とザンド時代、イランの白人の領土にはさまざまなハン国が形成された。アガ・モハマド・カーンは、これらの地域を本土の領土と同様に不可欠なものと考え、イランに再編入することを目指した。彼の主な標的の一つはグルジアであり、彼はイランの主権にとって重要であると考えていた。彼はグルジア国王エレクル2世に対し、1783年のロシアとの条約を破棄し、ペルシアの宗主権を再受諾するよう要求したが、エレクル2世はこれを拒否した。これに応じてアガ・モハマド・カーンは軍事作戦を開始し、現在の
アルメニア、アゼルバイジャン、ダゲスタン、イグディルを含む様々な白人領土に対するイランの支配を再確認することに成功した。彼はクルツァニシの戦いで勝利を収め、トビリシの占領とグルジアの効果的な再征服につながりました。
[55]1796年、ジョージアでの遠征の成功から帰還し、何千人ものグルジア人捕虜をイランに移送した後、アガ・モハマド・カーンは正式にシャーに戴冠した。彼の統治は、1797 年にジョージアに対する新たな遠征を計画中に暗殺され、短くなりました。彼の死後、
ロシアは地域の不安定に乗じた。1799年にロシア軍がトビリシに入り、1801年までに事実上グルジアを併合した。この拡大はロシア・ペルシア戦争(1804年から1813年および1826年から1828年)の始まりを示し、グリスタンおよびトルクメンチャイの条約に規定されているように、最終的に東ジョージア、ダゲスタン、アルメニア、アゼルバイジャンのロシアへの割譲につながった。したがって、現在のアゼルバイジャン、グルジア東部、ダゲスタン、アルメニアを含むアラス川以北の領土は、19世紀にロシアに占領されるまでイランの一部であり続けた。
[56]ロシア・ペルシャ戦争とコーカサスにおける広大な領土の正式な喪失に続いて、人口動態の大きな変化が起こりました。1804 ~ 1814 年と 1826 ~ 1828 年の戦争により、白人のムハージルとして知られるイラン本土への大規模な移住が始まりました。この運動には、アイラム人、カラパパク人、チェルカシア人、シーア派レズギ人、その他のトランスコーカサス人のイスラム教徒など、さまざまな民族グループが含まれていました。
[1804]年のガンジャの戦いの後、多くのアイラム人とカラパパク人がイランのタブリーズに再定住した。1804年から1813年の戦争中、そしてその後の1826年から1828年の紛争中、新たに征服したロシア領土からこれらのグループの多くが現在のイラン西アゼルバイジャン州のソルドゥズに移住した。コーカサスにおけるロシアの軍事活動と統治問題により、多数のイスラム教徒と一部のグルジア人キリスト教徒がイランに亡命した
[58] 。
[59]1864 年から 20 世紀初頭にかけて、コーカサス戦争におけるロシアの勝利に続いて、さらなる追放と自発的な移住が発生しました。これにより、アゼルバイジャン人を含む白人イスラム教徒、他のトランスコーカサス人イスラム教徒、そしてチェルカシア人、シーア派レズギ人、ラック族などの北コーカサス人集団がイランとトルコに向けてさらに移動することになった。
[これら]の移民の多くはイランの歴史において重要な役割を果たし、19世紀後半に設立されたペルシア・コサック旅団の重要な部分を形成した。
[60]1828年のトルクメンチャイ条約は、イランから新たにロシアが支配した地域へのアルメニア人の再定住も促進した。歴史的にはアルメニア東部ではアルメニア人が多数派であったが、
ティムールの遠征とその後のイスラム支配によって少数派となった
[61] 。
[62]ロシアのイラン侵攻により民族構成はさらに変化し、1832年までに東アルメニアではアルメニア人が多数派となった。この人口動態の変化は、1877年から1878年のクリミア戦争と露土戦争の後にさらに強固になった。
[63]この期間中、イランはアリー・シャー神父の下で西側の外交関与が増加した。彼の孫であるモハマド・シャー・カジャールはロシアの影響を受け、ヘラートを占領しようとしたが失敗した。モハメド・シャーの後を継いだナセル・アルディン・シャー・カジャールはより成功した統治者となり、イラン初の近代的な病院を設立した。
[64]1870年から1871年にかけて起きたペルシャの大飢饉は壊滅的な出来事で、約200万人が死亡した。
[65]この時期はペルシャの歴史における重要な転換点であり、19世紀後半から20世紀初頭のシャーに対するペルシャ立憲革命につながった。挑戦にもかかわらず、シャーは 1906 年に限定憲法に譲歩し、ペルシャを立憲君主制に変え、1906 年 10 月 7 日の最初のマジュリス (議会) の召集につながりました。1908年にイギリスがフゼスターンで石油を発見すると、特に
大英帝国によるペルシャに対する外国の利益が強化された(ウィリアム・ノックス・ダーシーとアングロ・イラン石油会社(現BP)に関連)。この時期は、グレートゲームとして知られる、ペルシャを巡るイギリスとロシアの地政学的な対立によっても特徴づけられました。1907 年の英露条約により、ペルシャは勢力圏に分割され、国家主権が損なわれました。
第一次世界大戦中、ペルシャはイギリス軍、オスマン帝国軍、ロシア軍に占領されましたが、ほぼ中立を保っていました。第一次世界大戦後と
ロシア革命後、イギリスはペルシアに保護領を設立しようとしたが、最終的には失敗した。ギーラーンの立憲主義運動とガージャール政府の弱体化によって浮き彫りになったペルシャ国内の不安定は、レザー・カーン、後のレザー・シャー・パフラヴィーの台頭と、1925年のパフラヴィー王朝の設立への道を切り開いた。 極めて重要な1921年の軍事クーデターは、ペルシャ・コサック旅団のレザー・カーンとセイエド・ジアエディン・タバタバイによるこの政策は、当初はガージャール王朝を直接打倒するのではなく、政府関係者を統制することを目的としていた。レザー・カーンの影響力は増大し、首相を務めた後、1925年までにパフラヴィー王朝の初代シャーとなった
[66] 。